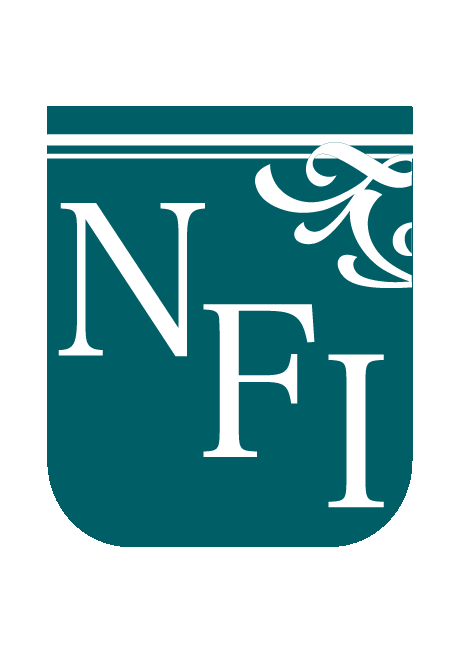New Food Industry 2025年 67巻 4月号
原著
オオイタドリ若芽エキス末配合グルコサミン食品による膝関節への影響
-無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験のサブグループ解析-
前野 沢郎(MAENO Takuro), 落谷 大輔(OCHITANI Daisuke), 柿沼 俊光(KAKINUMA Toshihiro), 宮下 博樹(MIYASHITA Hiroki), 金子 俊之(KANEKO Toshiyuki)
Effect of Glucosamine Food Containing Polygonum sachalinense Sprout Extract Powder on Knee Joints: A Subgroup Analysis of a Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group Study
Authors: Takuro Maeno 1*, Daisuke Ochitani 2, Toshihiro Kakinuma 3, Hiroki Miyashita 4, Toshiyuki Kaneko 5
* Corresponding author: Takuro Maeno
Affiliated institutions:
1 MYCARE Co., Ltd. [Ichigaya-Honmura-cho 2-5, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0845, Japan]
2 Huma R&D Co., Ltd. (Currently: BHN Co., Ltd) [Ichigo Kanda-Nishiki-cho BLG 6F Kanda-Nishiki-cho 1-16, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0054, Japan]
3 ORTHOMEDICO Inc. [Sumitomo Realty & Development Korakuen BLG 2F Koishikawa 1-4-1, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan]
4 Clinical Support Corporation Ltd. [TG-Sapporo BLG 8F, Minami 1 Nishi 8, Chuo-ku, Sapporo-City, Hokkaido 060-0061, Japan]
5 Tokyo Skytree Station Medical Clinic [Ryobi BLG 4F Mukojima 3-33-13, Sumida-ku, Tokyo 131-0033, Japan]
Abstract
Background and Aim
The powdered extract from the sprout of Polygonum sachalinense has been traditionally utilized for pain relief. This study aimed to investigate the efficacy of a food product containing glucosamine and powdered Polygonum sachalinense sprout extract in middle-aged and older individuals with self-reported knee discomfort, with a focus on its potential application in the functional food industry.
Materials and Methods
A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial was conducted with 200 healthy Japanese men and women aged 40–75 years who reported knee discomfort. Participants consumed either the test food or a placebo daily for 6 weeks. The primary efficacy endpoint was evaluated using the Japanese Knee Osteoarthritis Measure (JKOM) questionnaire, and the secondary endpoint was assessed using a Visual Analogue Scale (VAS) questionnaire consisting of 12 items. Subgroup analyses were performed to identify the population with the highest response to the intervention.
Results
Of the 200 participants, 199 completed the study. While the primary analysis did not show significant differences between the test food and placebo groups, subgroup analysis revealed significant improvements in 99 participants with baseline VAS scores ≥ 65.6 mm. Improvements were noted in JKOM Survey II (knee pain and stiffness) and Survey III (daily life performance, including Q9, Q10, and Q16). Secondary endpoint analysis demonstrated significant improvement in pain during traditional Japanese sitting.
Conclusion
The findings suggest that the food product containing glucosamine and powdered Polygonum sachalinense sprout extract has potential as a functional food product to support knee health in individuals with self-reported knee pain. These results could inform the development of new products in the functional food industry.
日本は高齢化率が高く,超高齢社会に突入しているため,加齢に伴う疾患が増加しており,その発症を予防する対策が十分機能していないことが問題視されている。高齢者の生活の質(QOL)の障壁となっていることの一つとして,腰痛や関節痛など移動機能障害を伴い,日常行動を制限することがある。中でも,膝の痛みを訴える高齢者は非常に多い。Yoshimuraらの調査結果に基づき,変形性膝関節症(膝OA)診療ガイドライン2023では,国内にレントゲン学的な膝OAの患者は約2,500万人と推定されている1–3)。年齢別の男性の罹患率をみると,40歳台では9.1%程度であるが,50歳台で24.3%,60歳台で35.2%,70歳台で48.2%,80歳以上では51.6%と推計され,年齢と共に増加する。女性の罹患率は男性に比べて高く,60歳台で57.1%,70歳台で71.9%,80歳以上では80.7%に達する。日本人の後期高齢者の半数以上はレントゲン的な膝OAに罹患していることになる。内閣府の高齢社会白書によると2022年時点での75歳以上の全人口に対する割合は15.5%であり,2030年には18.8%に達すると推計されている4)。後期高齢者が今後さらに増加することを踏まえると,膝OAとの診断には至っていないが痛みや違和感を訴えている“予備軍”が増加することは否定できない。この予備軍が膝の健康を維持し,歩行可能な状態を維持することはQOLを維持する上で重要である。
原 著
簡易食事調査票「栄養価日記 (Calorie and Nutrition Diary: CAND)」を用いた栄養調査: 簡易型自記式食事歴法質問票(brief-type self-administered diet history questionnaire: BDHQ) との比較
馬場 亜沙美(BABA Asami) ,山本 和雄(YAMAMOTO Kazuo) ,鈴木 直子(SUZUKI Naoko), 水野 将吾(MIZUNO Shogo),齋藤 憲司(SAITO Kenji)
Nutritional Survey Using a Simple Dietary Questionnaire “Calorie and Nutrition Diary (CAND)”: Comparison with the brief-type self-administered diet history questionnaire (BDHQ)
Authors: Asami Baba 1*, Kazuo Yamamoto 1, Naoko Suzuki 1, Shogo Mizuno 2, and Kenji Saito 2
* Corresponding author: Asami Baba1
Affiliated institutions:
1 ORTHOMEDICO Inc.
2 Yuurea Inc.
Abstract
Objective:
Despite the fact that nutrition and diet are closely related to health, not many people recognize the importance of improving dietary habitation in maintaining health. Against this background, in order to promote improvements in the diet of the Japanese, there is a need to develop methods that make it easy to grasp their own diet. In Japan, the “Calorie and Nutrition Diary (CAND)” was developed as a simple dietary questionnaire. However, there are currently few studies that have examined its characteristics. Therefore, the aim of this study was to re-evaluate the characteristics of the CAND by comparing the nutrient intake estimated from the CAND and the brief-type self-administered diet history questionnaire (BDHQ).
Methods:
This was a cross-sectional observational study. The participants were men and women in their 20s or ≥50s who were judged to have no underlying diseases based on their self-reports. The study participants were asked to record their daily meals at home using the CAND for seven consecutive days. In addition, they were also asked to answer the BDHQ on the seventh day of recording using the CAND. Correlation analysis was conducted on the nutrient intake estimated from the CAND and BDHQ.
Results:
A total of 170 participants were included in the analysis: 76 people in their 20s (38 women) and 94 people in their ≥50s (47 women). A significant positive correlation was confirmed for all 90 items, excluding two items for which no intake was confirmed. On the other hand, the estimated nutrient intake using CAND was higher than that using BDHQ. When comparing the correlation analysis of the 20s and ≥50s groups, the correlation between CAND and BDHQ was weaker in the 20s group than in the ≥50s group.
Conclusions:
The results of the correlation analysis with BDHQ supplemented the validity of CAND as a simple dietary questionnaire. There was a possibility that the estimated intake amount would be overestimated using CAND rather than BDHQ. In addition, when conducting a dietary survey of young people using CAND, it was shown that there was a possibility of being affected by interday variation and deviating from habitual nutrient intake.
抄録
目的:
栄養・食生活は,健康状態と密接に関係しているにもかかわらず,食生活の改善が健康維持において重要であることを認識している者は少ない。このような背景から,日本人の食生活の改善を促進するためには,食事内容を簡便に把握することができる方法の整備が求められている。日本では簡易的な食事調査票として,「栄養価日記 (Calorie and Nutrition Diary: CAND)」が開発されたが,その特徴について検討した研究は乏しい現状がある。そこで本研究ではCANDと簡易型自記式食事歴法質問票 (brief-type self-administered diet history questionnaire: BDHQ) から推定された栄養素等摂取量を比較することによって簡易食事調査票としてのCANDの特徴を再評価することを目的とした。
方法:本研究は横断的観察研究であり,自己申告により基礎疾患が無いと判断できる20代あるいは50代以上の男女を対象とした。研究参加者には,連続する7日間,自宅にてCANDを用いて自身の1日の食事について記録させ,記録期間の最終日である7日目にBDHQについても回答させた。CANDおよびBDHQから推定された栄養素等摂取量の相関解析を実施した。
結果:最終的に20代76名 (女性38名),50代以上94名 (女性47名) の計170名が解析に含まれた。摂取が認められなかった2項目を除く90項目すべてで有意な正の相関関係が確認された。一方で,CANDで推定された栄養素等摂取量はBDHQよりも多かった。20代および50代以上の集団における相関解析を比較すると,20代の集団では50代以上の集団と比較して,CANDおよびBDHQの相関関係は弱かった。
結論:
BDHQとの相関解析の結果から,簡易的な食事調査票としてのCANDの妥当性が補完された。CANDはBDHQよりも推定摂取量が過大評価される可能性があった。また,CANDを用いて若年層における食事調査を実施する場合,日間変動による影響を受けて習慣的な栄養素等摂取量と乖離する可能性があることが示された。
シリーズ EQUATOR Networkが提供するガイドラインの紹介
Guidelines for Reporting Outcomes in Trial Protocols The SPIRIT-Outcomes 2022 Extensionの和訳
著者
Nancy J. Butcher 1, 2, Andrea Monsour 1, Emma J. Mew 1, 3, An-Wen Chan 4, David Moher 5, 6, Evan Mayo-Wilson 7, Caroline B. Terwee 8, 9, Alyssandra Chee-A-Tow 1, Ami Baba 1, Frank Gavin 10, Jeremy M. Grimshaw 11, 12, Lauren E. Kelly 13, 14, Leena Saeed 1, Lehana Thabane 15, Lisa Askie 16, Maureen Smith 17, Mufiza Farid-Kapadia 1, Paula R. Williamson 18, Peter Szatmari 19, 20, Peter Tugwell 6, 12, 21, 22, Robert M Golub 23, Suneeta Monga 2, 20, Sunita Vohra 24, Susan Marlin 25, 26, Wendy J Ungar 1, 27, Martin Offringa 1, 27, 28
翻訳
馬場 亜沙美(BABA Asami),鈴木 直子(SUZUKI Naoko),野田 和彦(NODA Kazuhiko), 波多野 絵梨(HATANO Eri),髙橋 徳行(TAKAHASHI Noriyuki),新林 史悠(SHINBAYASHI Fumiharu) , 板橋 怜央(ITABASHI Reo) ,柿沼 俊光(KAKINUMA Toshihiro),山本 和雄(YAMAMOTO Kazuo)
Guidelines for Reporting Outcomes in Trial Protocols The SPIRIT-Outcomes 2022 Extension
Authors: Nancy J. Butcher 1, 2, Andrea Monsour 1, Emma J. Mew 1, 3, An-Wen Chan 4, David Moher 5, 6, Evan Mayo-Wilson 7, Caroline B. Terwee 8, 9, Alyssandra Chee-A-Tow 1, Ami Baba 1, Frank Gavin 10, Jeremy M. Grimshaw 11, 12, Lauren E. Kelly 13, 14, Leena Saeed 1, Lehana Thabane 15, Lisa Askie 16, Maureen Smith 17, Mufiza Farid-Kapadia 1, Paula R. Williamson 18, Peter Szatmari 19, 20, Peter Tugwell 6, 12, 21, 22, Robert M Golub 23, Suneeta Monga 2, 20, Sunita Vohra 24, Susan Marlin 25, 26, Wendy J Ungar 1, 27, Martin Offringa 1, 27, 28
Translators: Asami Baba 1*, Naoko Suzuki 1, Kazuhiko Noda 1, Eri Hatano 1, Noriyuki Takahashi 1, Fumiharu Shinbayashi 1, Reo Itabashi 1, Toshihiro Kakinuma1, Kazuo Yamamoto 1
* Corresponding author: Asami Baba
Affiliations (Authors):
1 Child Health Evaluative Sciences, The Hospital for Sick Children Research Institute, Toronto, Ontario, Canada
2 Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
3 Department of Chronic Disease Epidemiology, School of Public Health, Yale University, New Haven, Connecticut
4 Department of Medicine, Women’s College Research Institute, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
5 Centre for Journalology, Clinical Epidemiology Program, Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Ontario, Canada
6 School of Epidemiology and Public Health, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada
7 Department of Epidemiology, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill
8 Amsterdam University Medical Centers, Vrije Universiteit, Department of Epidemiology and Data Science, Amsterdam, the Netherlands
9 Department of Methodology, Amsterdam Public Health Research Institute, Amsterdam, the Netherlands
10 public panel member, Toronto, Ontario, Canada
11 Clinical Epidemiology Program, Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Ontario, Canada
12 Department of Medicine, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada
13 Department of Pharmacology and Therapeutics, University of Manitoba, Winnipeg, Canada
14 Children’s Hospital Research Institute of Manitoba, Winnipeg, Canada 15 Health Research Methods, Evidence, and Impact, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada
16 NHMRC Clinical Trials Centre, University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia
17 patient panel member, Ottawa, Ontario, Canada
18 MRC-NIHR Trials Methodology Research Partnership, Department of Health Data Science, University of Liverpool, Liverpool, England
19 Cundill Centre for Child and Youth Depression, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Ontario, Canada
20 Department of Psychiatry, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
21 Bruyère Research Institute, Ottawa, Ontario, Canada
22 Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Ontario, Canada
23 Department of Medicine, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois
24 Departments of Pediatrics and Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta, Edmonton, Canada
25 Clinical Trials Ontario, Toronto, Canada
26 Department of Public Health Sciences, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada
27 Institute of Health Policy, Management, and Evaluation, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
28 Division of Neonatology, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
Affiliated institution (Translators)
1 ORTHOMEDICO Inc.
[2F Sumitomo Fudosan Korakuen Bldg.,1-4-1 Koishikawa,Bunkyo-ku,Tokyo,112-0002,Japan.]
本項について
本稿は,EQUATOR Networkが提供するガイドラインの一つである「Guidelines for Reporting Outcomes in Trial Protocols The SPIRIT-Outcomes 2022 Extension」の本文を翻訳したものである。なお,付録※は原文(doi: 10.1001/jama.2022.21243)にアクセスして参照する。
要約 [Abstract]
重要性 【IMPORTANCE】
試験プロトコルに試験結果に関する完全な情報を記載することは,規制当局の承認を得るため,標準化された試験実施を確保するため,研究の無駄を省くため,そして試験方法の透明性を提供し,試験の再現,批判的評価,試験結果の正確な報告と解釈,知識の統合を促進するために極めて重要である。しかし,どのようなアウトカム特異的情報を含めるべきかについての推奨は多様で一貫性がない。透明で再現性のあるアウトカムの選択,評価,解析を促進する報告方法を改善するためには,臨床試験プロトコルにどのようなアウトカム特異的情報を記載すべきかについて,具体的で統一されたガイダンスが必要である。
目的 【OBJECTIVE】
標準プロトコル項目と統合することにより,臨床試験プロトコルにおけるアウトカムを記述するための,エビデンスとコンセンサスに基づく統一された基準を開発する: Recommendations for Interventional Trials(SPIRIT)2013声明と統合する。 エビデンスレビュー 【EVIDENCE REVIEW】 Enhancing the Quality and Transparency of Health Research(EQUATOR)の方法論的枠組みを用いて,SPIRIT 2013声明の拡張版であるSPIRIT-Outcomes 2022は,下記の通り作成された。
(1)専門家との協議によるアウトカム報告項目の候補の作成と評価,専門家の募集,MEDLINEおよびCochrane Methodology Registerの電子データベース検索,灰色文献検索,参考文献リスト検索により特定された臨床試験のアウトカム報告に関する既存のガイダンス(2018年3月19日以前10年以内に公表されたもの)のスコーピングレビューにより作成された。
(2)22カ国124人のパネリストによる3回の国際デルファイ投票プロセス(2018年11月~2019年2月)を実施し,追加項目の評価と特定を行った。
(3)25人のパネリストが参加した対面コンセンサス会議(2019年4月9日~10日)を実施し,臨床試験プロトコルで扱うべきアウトカム特異的報告の必須項目を特定した。
調査結果 【FINDINGS】
スコーピングレビューおよび専門家との協議により,臨床試験プロトコルで扱うべきアウトカム特異的報告に関連する108の推奨事項が特定され,その大部分(72%)はSPIRIT 2013声明には含まれていなかった。デルファイ調査の結果,19の項目がコンセンサス会議での更なる評価基準を満たし,SPIRIT-Outcomes 2022拡張版に含めることが可能となった。コンセンサス会議での議論の結果,SPIRIT 2013声明チェックリスト項目をさらに詳細にした9項目が得られた。この9項目は,臨床試験プロトコルにおいて,主要アウトカム,副次的アウトカム,その他のアウトカムの選択を完全に定義し,正当化すること(SPIRIT 2013声明チェックリスト項目12),サンプルサイズの計算に使用する主要アウトカムの治療群間目標差を定義し,正当化すること(SPIRIT 2013声明チェックリスト項目14),アウトカムを評価するために使用する評価尺度の応答性を記述し,アウトカム評価者についての詳細を提供すること(SPIRIT 2013 声明チェックリスト項目18a),解析または結果の解釈に関連する多重性を考慮するための計画された方法を記述すること(SPIRIT 2013 声明チェックリスト項目20a)に関するものである。
結論と関連性 【CONCLUSIONS AND RELEVANCE】
SPIRIT-Outcomes 2022は,SPIRIT 2013声明を拡張したもので,すべての臨床試験プロトコルで扱うべき9つのアウトカム特異的報告項目を示しており,臨床試験の有用性,再現性,透明性の向上に役立ち,試験結果の選択的非報告のリスクを最小限に抑える可能性がある。
連載
在来種のジャガイモ NATIVE POTATOES
瀬口 正晴(SEGUCHI Masaharu),楠瀬 千春(KUSUNOSE Chiharu)
人は太古の昔から塊茎を食べてきた。実際,少数ではあるが熱心な人類学者の一団は,調理された塊茎全般が,人類を他の霊長類から引き離す決定的な役割を果たしたと主張している。彼らによれば,(おそらくアフリカ産の)塊茎は,獲得するのに追いかける必要がなく,しかもほとんど噛む必要もなく食べられる食材だった。調理することで,デンプンは甘く魅力的な食品に変わり,そのカロリーも吸収されやすかった。加えて,塊茎は保護された一箇所に保管する必要があったため,「家庭生活」が始まった。これらすべてが,大きな脳,小さな歯,現代的な四肢のプロポーション,さらには男女の絆の進化を促したのだと,支持者たちは言う。 これは,いくつかのありふれた植物に課すには大きな告発のように思えるかもしれないが,しかし,ハーバード大学の人類学者リチャード・ランガムと彼の同僚たちは,調理された塊茎が人類の進化にとって極めて重要であったと確信している。彼らは,どの種が人類誕生のきっかけになったかは推測していないが,この章の主題は有力な可能性のように思われる。現代の植生が約200万年前のアフリカ南部と東部の植生を反映していると仮定すると,他に可能性があるのはヤマイモ,マラマ,ヤムビーン,Vigna vexillata(魅力的なマメ科植物),そしてタイガーナッツ(Cyperus esculentus)くらいだろう。人類が誕生した地域の可能性としてあまり知られていないのは,サツマイモの親戚(Ipomoea種),水根(Fockea種),Raphionacme burkei,ウリ科植物のCoccinia rehmanniiとCoccinia abyssinicaのカップルなどである。
連載 乳および乳製品の素晴らしさ 第16回
牛乳に含まれる脂質の不思議
「バターに含まれるトランス型脂肪酸の起源と安全性」
齋藤 忠夫(SAITO Tadao)
著者が2006年の夏にアメリカ出張した際に,ホテルの朝食でパンに塗るバターが無いことに気が付きました。全米のホテルでバターが撤去されたかは定かではありませんが,「ホテルからバターが一掃された」のは大事件でした。当時は牛乳中に含まれるトランス(型)脂肪酸(Trans Fatty Acid: TFA)は悪者で,牛乳脂肪から製造したバターを食べるのを多くのアメリカ国民が躊躇している時期でした。その後,アメリカではホテルだけでなくレストランチェーンも,消費者からの訴訟リスクを回避したり,政府の規制を先取りする目的に加えて,ライバル店との違いを打ち出す狙いもあり,トランス脂肪酸を含むバターやショートニングをメニューから外して行きました。このように,ホテル業界に続いて外食業界においてもトランス脂肪酸不使用の動きが加速していったのでした。牛乳脂肪にはトランス脂肪酸がわずかに含まれており,従来より,乳脂肪の過剰摂取は心臓病との関連で問題視されることがありました。 今回は乳脂肪に含まれるトランス脂肪酸の起源や性質の理解を通して,バターやマーガリンの安全性や今後の将来性について考えてみたいと思います。
コラム
リーダーのあるべき姿 織田信長
信長の最大級の危機稲生の戦い
坂上 亮
義務教育の中でも必ず学ぶ人物である織田信長。歴史の教科書では表舞台でのデビュー戦となる一五六〇年の桶狭間の戦い以降しか記述されない事が多い。しかし、この戦いの何年も前に信長が最大級の危機を乗り切っていた。一五五六年に起きた弟の謀反、稲生の戦いをご存知だろうか。 そもそも稲生の戦いとは織田信長と彼の弟であった織田信行(媒体によっては信勝とも)の戦いでありまだ尾張国内を掌握できていない信長にとって非常に危険な戦いであった。信長の置かれた状況を中心に戦いの経過やその後を説明し、そこから現代を生きる我々にも様々な学びがある事をこ紹介させていただく。